前書き
この本を手にとったのは、才能や努力といった言葉を、研究者がどのように捉えているかを知りたかったからだ。
本書の執筆者はフロリダ州立大学心理学部の教授である。
僕は小さい頃、特に小学生の頃だったと思うが、クラスにいつもテストで高得点を取っている生徒や、体育の授業で、例えば長距離走で良いタイムを出している生徒などを見て、羨んだ経験がある。(僕は長距離走が苦手であった)
そして、物事がうまくいかない時、自分には才能が無いからと考えたり、良い成績を収めている人を見て、彼らは生まれつき才能を持って生まれた、と考えていたことを覚えている。つまり、人は生まれながらにして平等ではないと考えていた。
今思い返すと、かなり後ろ向きな考えであったと思っている。
このように、僕は「生まれつき持った才能」というものが存在し、そして「人より秀でた才能を持って生まれた人間」には、平凡な人間はどんなに努力をしても太刀打ちできないと考えていた。
本書を手に取る前も、このように考えていた。
しかし、本書を読み終えてみて、これらの考えは間違っていたと認識した。それだけでも、本書を読んで良かったと思っている。
本書は今までの僕の考えをうまく訂正してくれた。すべてが覆されたというわけではなく、修正し、加筆してくれたような感覚だ。
本書を読んで得たことや気づいたこと、それらをできるだけ自分の言葉に置き換えながら書いていこうと思う。
コンフォートゾーンを抜ける
本書の中で、限界的練習という言葉が多く登場する。本書の一番のキーワードがこの限界的練習だと言ってもいい。
限界的練習とは、簡単にいえば超一流になるための練習のことだ。
本書にはその限界的練習の具体的な方法や、学生を対象とした実験などが数多く書かれている。
わかりやすいたとえ話をしたいと思う。
テニスサークルがあったとして、そこに参加してテニスをするとする。このテニスサークルで週に2、3回テニスをするとして、これを10年間続けたとしよう。
プロのテニスプレーヤーになれるだろうか。
答えは明白に不可能であるはずだ。
テニスが未経験の人にとって、テニスサークルに入ることで得られることは多々あるだろう。僕はテニスをやったことはないが、テニスサークルに入ってテニスを始めたら、飛んできたボールを打ち返すことはできるようになるだろう。おそらく、テニスを楽しむという段階には到達することができる。その自信はある。
しかし、プロのテニスプレーヤーには絶対になれない。年齢もあるが、たとえ僕が10代の少年であったとしても、テニスサークルだけでは絶対にプロのテニスプレーヤーにはなれない。
プロのテニスプレーヤーになるためには、多くのお金を必要とする専門の学校に入り、いわゆるテニスの英才教育を受けなければならない。
そしてその教育を受けた人間のすべてがプロのテニスプレーヤーになれるわけではなく、その中で多くの努力をした人間だけがプロになれるのだ。
ここで言いたいのは、プロのテニスプレーヤーになるためには専門の学校に入る必要があるということではなく、楽しむという段階をいくら長く続けても上達はしないということだ。
限界的練習には苦痛が伴う。本書でもそのようなことが書いてあったと記憶している。
コンフォートゾーン(快適と感じる状態)から抜けて練習をすることが、上達への第一歩であり、これが限界的練習の一部であると僕は理解した。
限界的練習の方法について
限界的練習をコンフォートゾーンから抜けることと書いたが、ただ辛い練習をすればよいというものではない。
日本人は我慢が美徳と考える風習があるためか、辛いことをしていることがそのまま成長につながると考えているように思う。これは僕自身の考えだ。
しかしこれは間違いだ。
コンフォートゾーン抜けて練習をするということは大前提として必要だが、いつまでも結果が出ないのにその練習を続けていくことに意味は無い。
つまり、もうひとつ成長に必要な重要な要素として、練習方法を考えるということがある。
興味深いことが本書に書いてあった。
オリンピックで人間が世界記録を塗り替え続けられることは、練習方法が改善され続けているからだ、と。
確かに大昔よりは今のほうが食べ物が充実していて、栄養状態も良くなっている。でもそれだけで人間が世界記録を塗り替え続けられていると考えるのは、明らかに簡単に考えすぎだ。
プロのスポーツ選手を見ればわかるが、必ずどの選手にもコーチが付いている。
このコーチが、選手に対してアドバイスをし、選手はそのアドバイスによって自分の弱いところを認識したり、強みをもっと伸ばすことができている。
自分の中だけで練習が完結してしまっていては、客観的な見方ができないので、どこをどのように変えていけばいいのか、つまりどのように練習すれば効果が出るのかがわからなくなる。
ただコンフォートゾーンを抜けてひたすら辛い練習をするのではなく、客観的な目線も取り入れて練習方法についても考えるということが、成長には欠かせないということだ。
心的イメージについて
心的イメージという言葉が本書では登場する。
心的イメージを僕の言葉で言わせてもらえば、意識しないでもできる技術のことだ。
例えばチェスのグランドマスター(チェスの世界チャンピオンのようなもの)が、チェスで相手と対戦する時、いちいちチェスのルールを確認しているわけがない。
チェス盤を見て、駒の位置を瞬時に把握し、その中で最善の一手をすぐに決定することができる。
ここに、チェスを始めたばかりのときに行った、駒がどのように動けるか考える、といったような次元は存在しない。
チェスのグランドマスターは、数え切れないほどのチェスの試合の経験から、このような状況のときにはこの一手が有効であるだろう、というようなイメージを頭の中で瞬時に作り出すことができる。
これは目に見える知識などではなく、経験や練習で培った目に見えにくい技術であり、これが心的イメージだ。
考えてみれば理解できる。
僕もこのようなブログ記事を書くことに最初はかなりの時間がかかってしまっていた。記事を書こうとすると、何から書けばいいのか、と考えたり、どのように書けばいいのか、と考えたりしてしまっていた。
もちろんそのような段階のときには、世の中の有識者の知識を借りて、例えば段落を作るという物理的な知識を得たりした。
そしてそのような物理的な知識を得つつ、記事や文章を書き続けていくうちに、考える時間は極端に少なくなった。
今こうして文章を書いているが、ブログを始めた頃よりは遥かに悩む時間は少なくなっている。
これは、経験を積むことができて、無意識にこのようにやればできるという心的イメージが付いたためだと考えている。
もちろん、これからもより良い文章をかけるようになるため練習や場数を踏んで行くわけだけれども、この心的イメージを向上させるためには、前述したコンフォートゾーンを抜けた状況での努力と、練習方法の改善が欠かせないものだと考えている。
 |
【中古】 超一流になるのは才能か努力か? /アンダース・エリクソン(著者),ロバート・プール(著者),土方奈美(訳者) 【中古】afb 価格:1,540円 |
コーチについて(ちょっと閑談)
ここで一息入れたい。
この章で書くことは、僕の実体験がベースとなっている。
もちろん、この「超一流になるのは才能か努力か?」という本を読んで自分が個人的に思ったことであり、本記事の趣旨には背いたことではない。
前章で、プロのスポーツ選手にはコーチが付いていると書いたが、このコーチを選ぶことがとても重要であると僕は感じたのだ。
コーチという言葉に語弊がある方は、何かのレッスンを受ける時に指導をしてくれる人のことを思い浮かべてほしい。
結論から言うと、見よう見まねで指導者っぽいことをしている人が存在する、ということだ。
そして、このような指導者っぽいことをしている人のもとでいくら練習に励んでも、上達はしない。
具体的な話をしよう。
僕は社会人劇団に所属していた。芝居は芝居でそれなりに充実したし、技術者として会社でプレゼンをする機会があるが、そのプレゼンのスキルも芝居で向上したと思っている。
この社会人劇団の活動で疑問に思ったのは、発声練習である。
所属していた社会人劇団の詳細はもちろん明かさないが、劇団の発声練習で「50m先にいる人に届けるイメージで文章を読む」や、「とある動物(食べ物のときもあり)になったイメージで文章を読む」といったものがあった。
完全に意味がないとは言わないが、このようなことをする前にやるべき練習がある、と僕は言いたい。
劇団を退団し、僕はボイストレーニングに行った。
ここで最初にやったことは、ひたすら呼吸を整え、腹式呼吸をすることであった。
ボイストレーナーは、声の基礎は呼吸なのだ、と教えてくれた。そしてその言葉に僕は何の疑問も感じなかった。なぜなら、僕は呼吸ができていなかったから。
生きていく上での最小限の呼吸はできていた(できていなければ生きていない)が、通りが良い声や耳に心地よい声を作り出すためには、まず呼吸ができていなければならない。
呼吸ができていないのに、50m先の人に届けるイメージで発声する、といったような応用練習を行っても、効果は薄いと考えるべきだ。
上から目線で申し訳ないが、所属していた社会人劇団の劇団員たちは、ほとんどが観客に届くほどの大きな声が出せる人がいなかった。
だから僕は、テクニックや応用の練習をする前に、基礎を固める練習(もっと基本的な練習)をするべきで、その劇団での練習方法は間違っていたと考えるに至った。
ボイストレーナーに劇団でどのような発声練習を行っていたか、と聞かれたことがあり、ありのままを答えたが、その際見よう見まねで練習を行っている団体はたくさんあるという言葉をもらい、今でも心に残っている。
知能指数(IQ)と自己充足的予言
本書ではたくさんの研究結果が書かれいるが、その中でも興味を引かれたのがIQと傑出した人物の関係だ。
IQが高い者たちが集まる「メンサ」という団体がある。
WIKIPEDIAから引用すると、メンサの定義は以下だ。
人口上位2%の知能指数 (IQ) を有する者の交流を主たる目的とした非営利団体である。高IQ団体としては、最も長い歴史を持つ。会員数は全世界で約12万人。支部は世界40か国。イギリス・リンカンシャーにあるケイソープ(英語版)に、本部(メンサ・インターナショナル)を持つ。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%B5
本書では、ノーベル賞受賞者にIQがメンサの入会資格に満たない人は数多く存在すると書かれていた。
そして、IQが高いほうが幼い頃に勉強がよくできたりすることは確かにあるが、長い人生の時間で考えれば、努力によって超一流になれるかどうかが決まると書かれている。
つまり、IQが影響するのは、スタート時点であり、小さい頃のみであるということだ。
そしてこれは、自己充足的予言を発生させてしまうと書かれている。
自己充足的予言の定義をは以下のようになっている。(コトバンクより引用)
ある社会的事象や状況に関して,誤った判断や思い込みなどが,新たな行動を引起し,その行動が当初の誤った判断や思い込みを現実化してしまう場合,当初に生じた判断や思い込みなどをさしていう。
https://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%85%85%E8%B6%B3%E7%9A%84%E4%BA%88%E8%A8%80-73078
つまり、IQは幼い頃のスタート時点でのみ影響することであるのに、このスタート時点で「自分は才能がない」と考えたり、もっとわかりやすく言えば、「自分はIQが低いから」と自分に(もしくは他者に)レッテルを貼られてしまうと、努力することさえ諦めてしまい、可能性を台無しにしてしまうということだ。
だから大事なことは、「○○を上手になりたい」や、「〇〇ができるようになりたい」と考えた時、まず努力の量によって結果が生まれると考えることだ。
はっきり言うが、才能の有無や、向き不向きばかりに目を走らせることはまったく無意味なことだ。
後書き
ボリュームのある本で読むのに苦労したが、読んで絶対に損のない本であると言い切れる。
たくさんの研究結果が書かれているので、もっと深く知りたいと思った方はぜひ手にとって読んでいただきたい。
この本をたくさんの人が読めば、誤った価値観が減っていくと思うし、適切な練習方法が広まって能力を高めることができる人が増えると思う。
僕自身もあらためて、練習方法や物事への取り組み方を見直すきっかけとなった。
以上です。
本記事を最後まで読んでいただき、ありがとうございました。







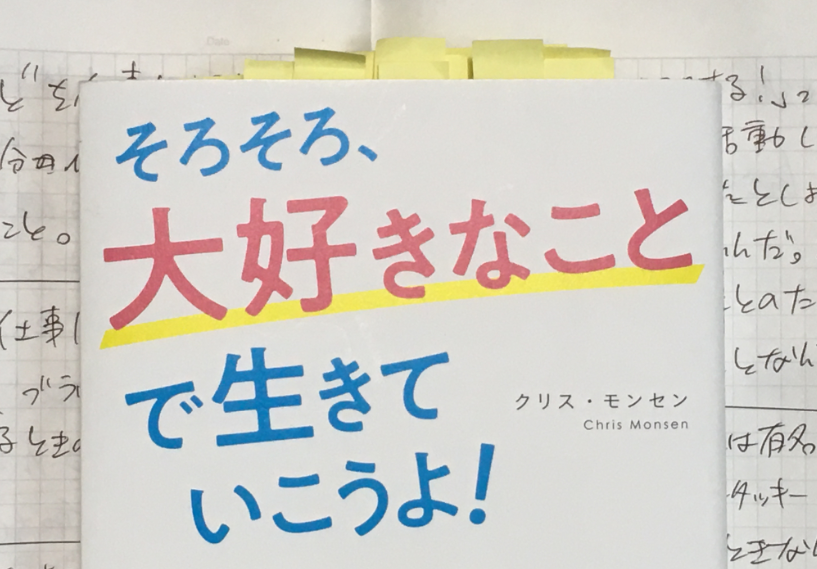
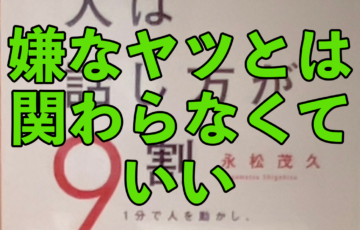
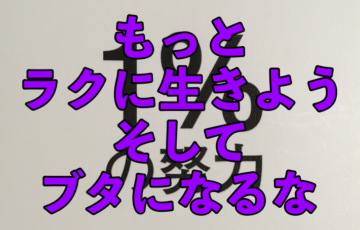

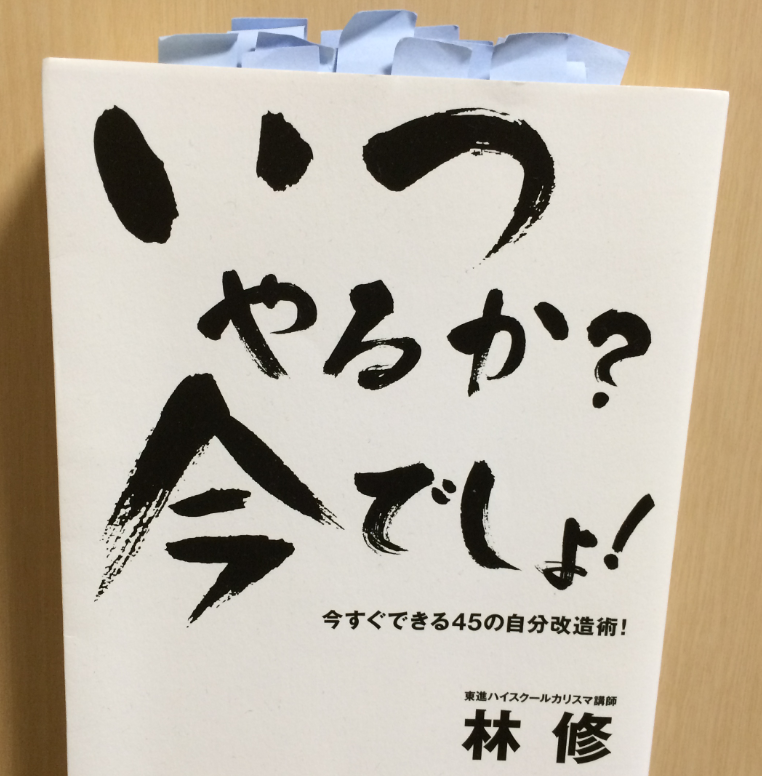



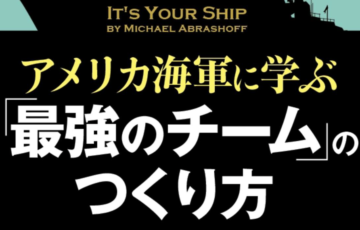
―100年時代の人生戦略-LIFE-SHIFT-eBook-リンダ・グラットン-アンドリュー・スコット-池村-千秋-本-2022-11-29-16-41-43-360x230.png)




